
「雷対策の判断基準が分からず不安…」
そんな先生方のお悩みを解決します。
近年、全国の学校で落雷事故が相次いでいます。令和6年4月には熊本県内の中学校で部活動中に生徒が落雷で負傷する事故が報告されました(文部科学省:学校事故の詳細調査報告書の共有についてより)。
この記事では 学校で実践できる雷対策チェックリスト をまとめました。すぐに使える形で整理しているので、日々の安全管理にそのまま役立てていただけます。
学校で落雷事故が起きやすい3つの理由
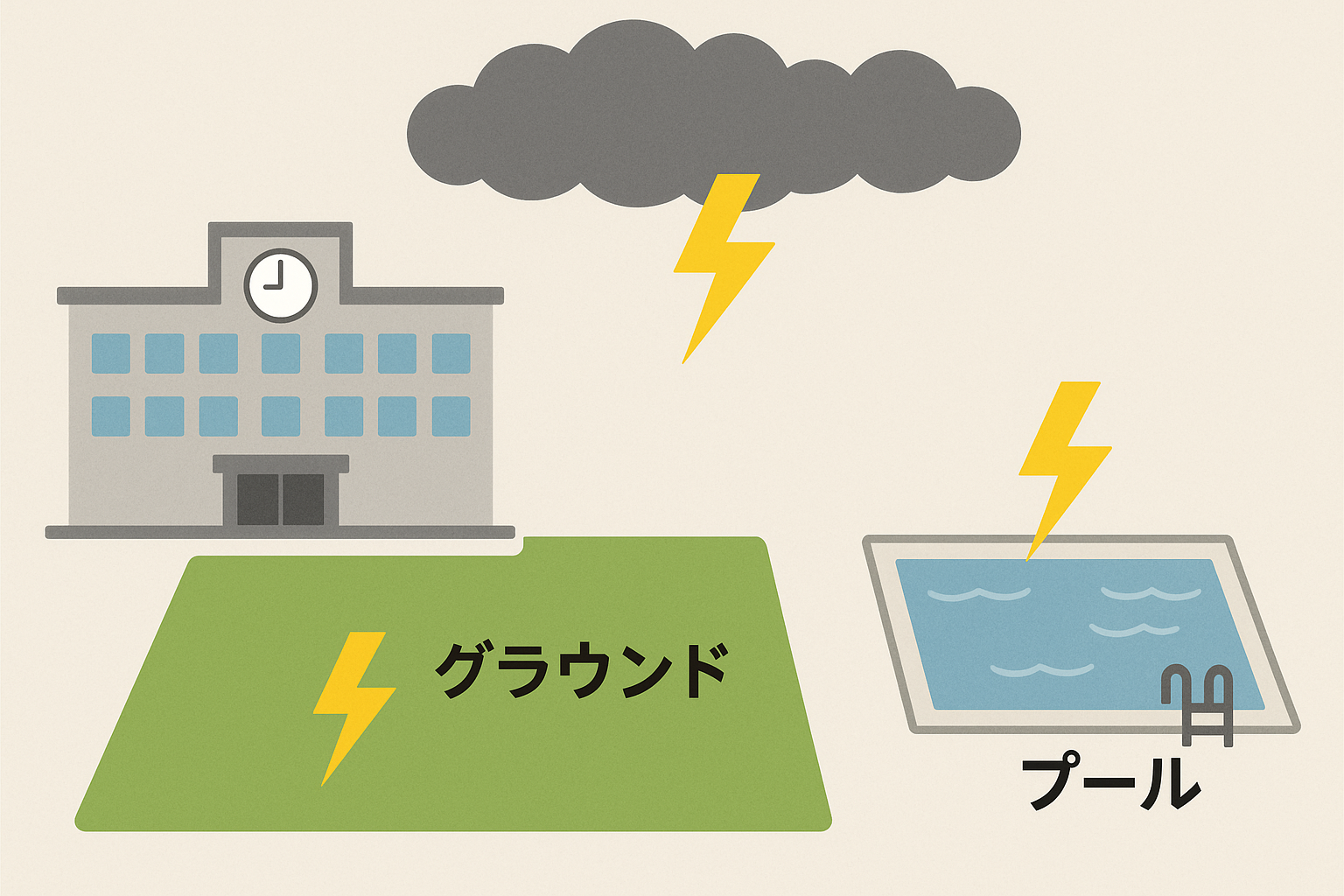
- 広い屋外スペース(グラウンドやプールなど)
- 多数の児童生徒を一斉に避難させる難しさ
- 天気予報だけでは突発的な雷を予測できない限界
過去には部活動中や登下校時に落雷事故が発生しています。だからこそ「事前に行動基準を決めておくこと」が命を守る鍵です。
より具体的な雷対策についてはこちら ↓
学校雷対策チェックリスト【段階別3ステップ】
ここからは 今日から始められる雷対策 をステップごとに確認しましょう。
🚨 ステップ1:緊急時の避難対応(即実行)
- 「雷鳴=即避難」を全校で徹底
- 避難責任者を事前に明確化
- 最寄りの安全避難場所を児童生徒に周知
- 授業や部活前に気象庁の雷情報を確認
⚡ ステップ2:定期点検と訓練の実施方法
- 避雷針や電気設備を担当者が点検
- 年間防災訓練に「雷避難」を組み込む
- 教職員会議で避難基準を繰り返し共有
- 保護者に「学校の雷対策方針」を説明
🔧 ステップ3:科学的安全強化(要予算)
- 「雷報」等の雷検知器導入検討
- 専門業者による詳細点検を依頼
- 校内放送システムと連動させ、雷検知と同時に自動アナウンスで避難を促す
次世代技術「雷報」で変わる学校の安全管理

従来は「雷鳴が聞こえたら避難」という経験則頼みでしたが、これでは判断が遅れることもあります。雷報は最大60km先の雷活動を検知し、音で即時に警告します。これにより数分〜数十分早く避難判断が可能になり、迷わず指示が出せます。
雷検知器について詳しく知る↓
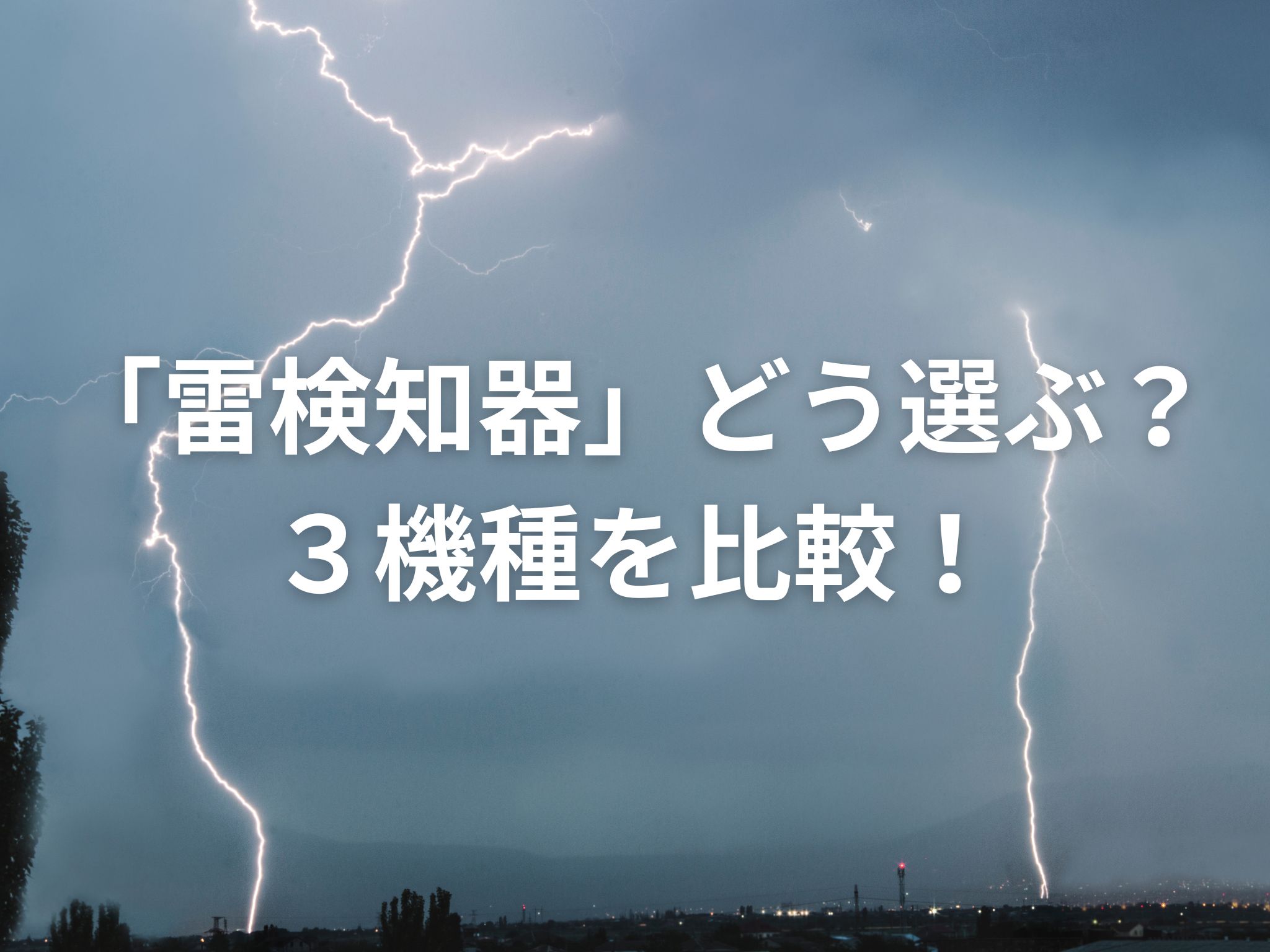
保護者との雷対策相談|想定される会話例と対応のポイント

「雷対策について保護者からこんな質問をされたらどう答える?」そんな不安を解消する会話例集です。事前に準備しておくことで、先生は自信を持って対応でき、保護者にも安心してもらえます。
活動中止の基準について

学校はどんな基準で活動を中止するのですか?

「雷鳴が聞こえたら即避難・活動中止」を基本方針としています。曖昧な判断を避け、子どもたちの安全を最優先に行動します。
授業や行事への影響について

急な雷で授業や部活が中止になった場合はどうなりますか?

事前に代替活動を準備しており、混乱を最小化します。体育は体育館での授業に切り替え、部活動は屋内練習メニューを実施します。
判断根拠について

雷報のような雷検知器があると、何が変わるのですか?

従来の「雷鳴が聞こえてから避難」では判断が遅れる場合がありました。雷報は最大60km先の雷活動を事前検知し、より安全な早期避難が実現できます。
学校雷対策で最優先すべき3つの行動【まとめ】
- 雷が聞こえたら即避難
- 月1回の点検・訓練を継続
- 科学的データで判断できる体制を整備
以上の3つを徹底し、子どもたちの安全を守る第一歩を、今から始めませんか?




